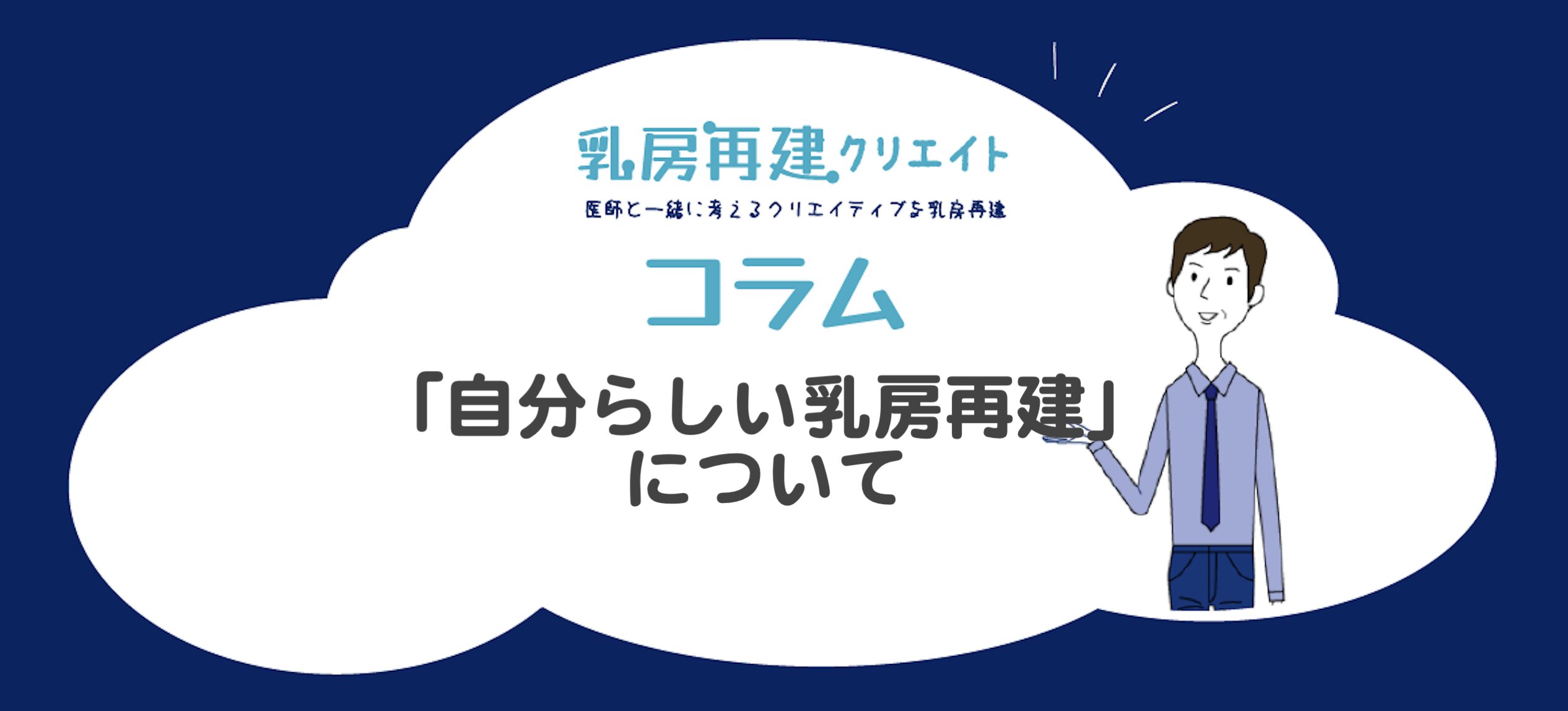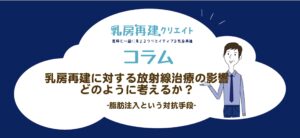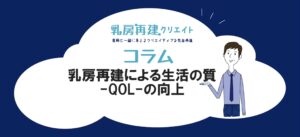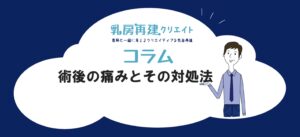「自分らしい乳房再建」について
実際の臨床の場面でにおいて、患者さんにとっては各選択肢のメリットとデメリットを限られた時間で正しくそして十分に理解することは難しいと思います。また患者には自分にとってベストだと思える選択肢は異なってきます。例えば、患者本人の希望は下着を着けた時の左右乳房の均等性の確保、体に新たなキズをつけたくないこと、あるいは仕事に一日でも早く復帰すること、あるいは経済的なことかもしれません。このような状況で医師の役割とは何かよく考えることがあります。
まず最初に思うことは、医療者側は意識的に中立的な立場で正しい情報を提供し、意思決定にバイアス(偏見的な見方)がかかりにくいよう努力することができるということです。ただ、これだけでは意思決定を外側から支援しているに過ぎないようにもみえてしまいます。
意思決定を行う主体はあくまでも患者や患者の代行者であり、医療者は「患者の意思決定」を外から支援するという関係性を想像してしまいます。しかし、このいわゆる説明的関係に基づくインフォームドコンセント(IC)は医療者がなるべく意思決定に関与しない姿勢を生み出してしまう、危うい構造を秘めているようにも思います。それによって説明責任はあるけども意思決定への参加をできるだけ回避したい医師側の欲求が顕在化していまうのです。
このシステムでは患者は意思決定主体者としての権利は保護される一方で、置き去りになってしまう状況が生まれてしまうという潜在的構造があります。
患者の好みや置かれた事情を探りながら治療法の選択肢を検討することは、患者の価値観、嗜好、環境に合った決断を促すことに役立ちます。また状況に応じてベストな治療法を選択するためには、患者の個々の危険因子や臨床的特徴と、患者の好みや目標とのバランスをとる必要があります。

そのようなことを考えていた日々の中でふとした偶然でShared Decision Making (SDM)という新しい意思決定スタイルを知ることがありました。SDMは話の着地点を医療者主導型で導いていくというよりは、これまで蓄積された信頼できるエビデンスを参照にしながら患者と医療者の間の協働的な話合いの中で共に自分らしい事項を模索していく決定スタイルです。

SDMを進めていく上で意思決定支援ツール(Decision Aid:DA)を使用するのが理想的だと言われています。しかし、日本に乳房再建のDAはありませんでした。
そこで乳房再建の分野においても、質の高いDAが必要であると考え、国際基準に則り、正しい手順で作成されたDAを作成しました。そのDAは「自分らしい乳房再建を決めるガイド」として、このサイトからダウンロードできます。
是非、参考にしていただければと思います。
今後、現在の乳房再建のような特殊な臨床状況においてSDMがもっと広く活用されるようになれば嬉しく思います。